新宿区早稲田/神楽坂にある漱石山房記念館に二度目の訪問。企画展『夏目家の人々』を観に行った。
soseki-museum.jpsoseki-museum.jp
上記ページに追加すると、
長女・筆子と松岡譲(作家)の間に生まれた四女・末利子。
末利子の夫が半藤一利(戦史研究家)
長男・純一の長男・房之助(漫画批評家)など、文化芸術分野の著名人が多い。
今のわたしは、漱石の世代の曽孫か玄孫(やしゃご)の方と近い世代。実際に著名な方の曾孫と交遊があるので、遠いと思っていた人が近くに感じられる、ちょっと不思議な気持ちになる。
●鑑賞メモ
・幼少期から思春期にわたって、家族が安定せず、継続的な愛着を持つ機会がそこなわれていた漱石にとって、自分がつくった家族との幸福な日々と、癒えない痛みや悲しみが伝わってくる展示内容だった。畏友と読んで親しく付き合った正岡子規への手紙の中で、
「小児の時分より"ドメスチツクハツピネス"という言は度外に付し居候へば」
とある。この時代の家族や結婚制度について「当時はよくあること」も多かっただろう。しかしだからといって「傷つかなかったわけじゃない」ということに気づいてハッとした。制度や慣習の違いはあれど、人間が感じる喜びや悲しみは変わらない。だから今も漱石の作品は古びない。
・前回来たときも思ったけど、「木曜会」という発想はおもしろい。以前働いていた職場で、代表に「お話聞かせていただきたい」、「意見交換がしたい」といっていろんな方が面会に来られるんだけど、全部対応していて、1件につき1〜2時間は話しこむから仕事が進まなくて、ほんとうにストレスだったことを思い出す。人脈形成も重要とはいえ、本人もそれなりに疲れて仕事が滞るので、とばっちりも食らうので、ダブルでストレス。門下生の進言で木曜会を開くことになったらしいが、きっとわたしのようなしんどい思いをしたんだろうと想像する。虚子に送った手紙の中にその様子が記されていて、おもしろい。
「木曜会がはじまる。小生来客に食傷して木曜の午後三時から面会日と定め候。妙な連中が落ち合ふ事と存候。ちと景気を見に御出被下座候」
木曜会メンバー https://soseki-museum.jp/soseki-natsume/surround-soseki/
東京在住に人でもなかなか知らないようなこと、漱石に興味を持ち始めた人にとってのちょっとした「へえ」がたくさんまぶしてある。たとえば、どうして記念館の中のカフェで空也もなかが食べられるんだろう?と思っていたら、Mapの中の「空也跡」に「漱石お気に入りの和菓子店。『吾輩は猫である』に空也餅が登場。現在の店舗は銀座」と解説がついている。以前は上野にあったのか。銀座の空也もなかの前を通ると、「予約分で終了しました」といつも張り紙をしてあったなと思い出す......そういう種類の「へえ」。
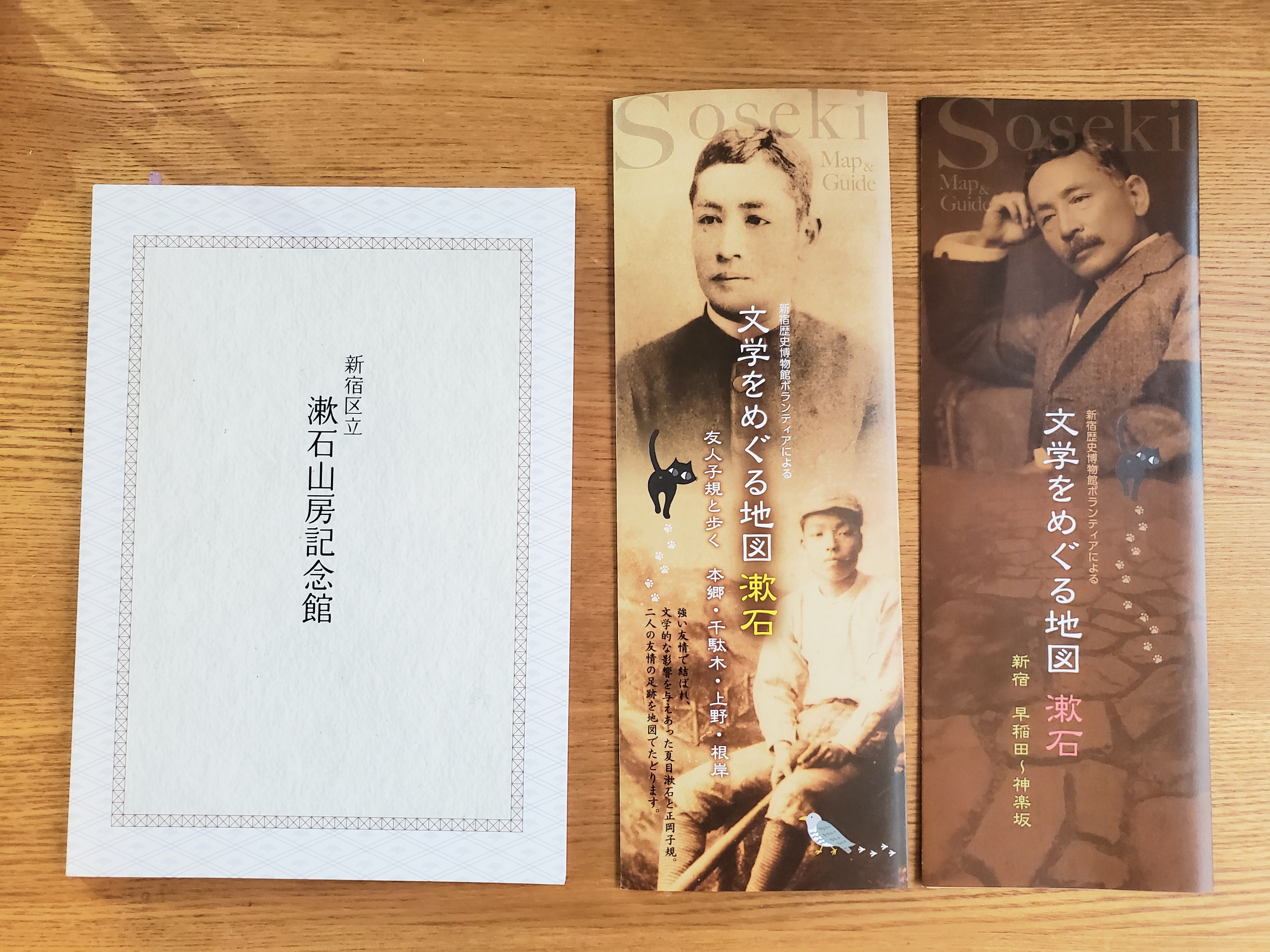
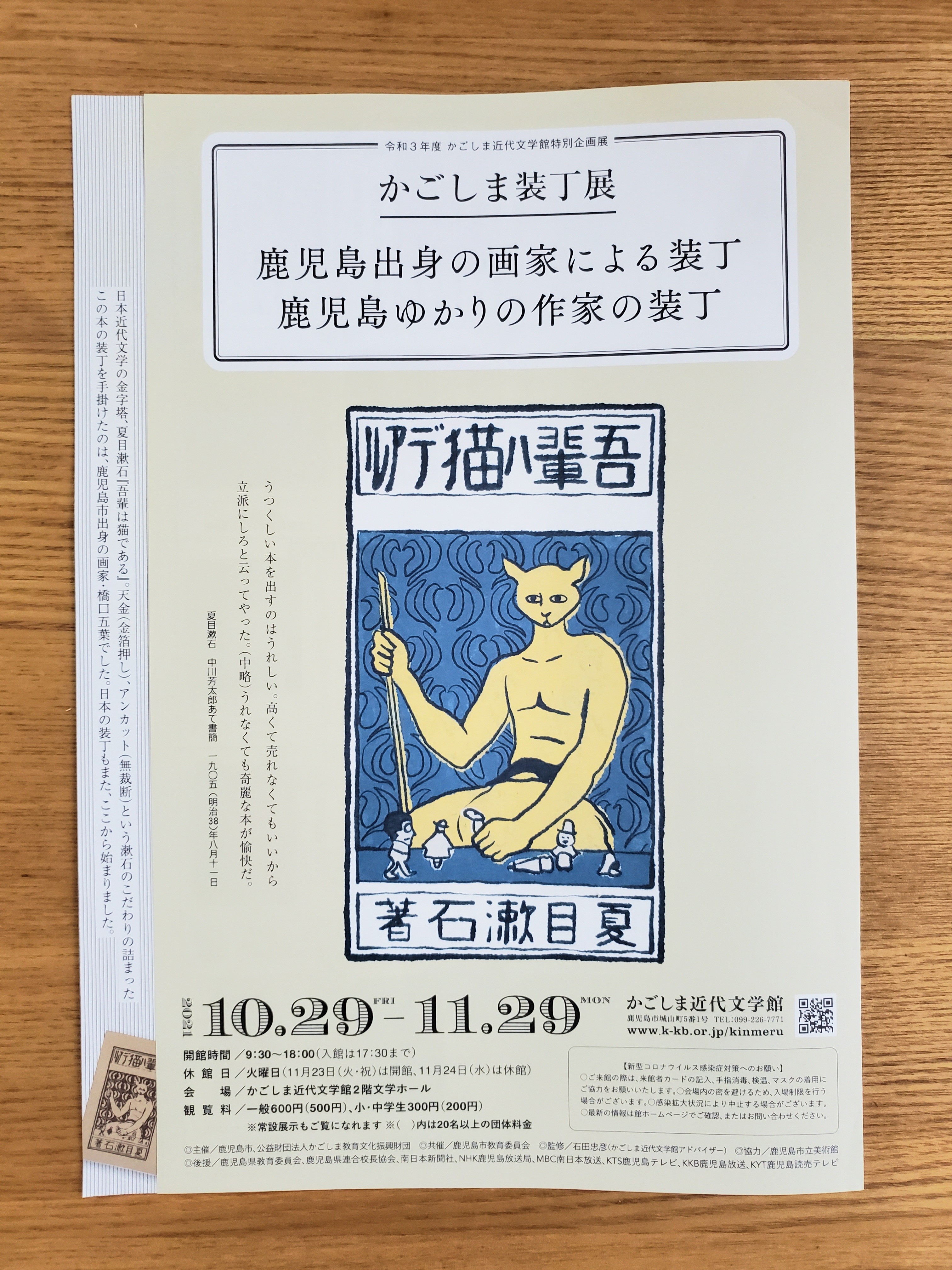
・少し前に、NHKラジオの朗読で放送されていた漱石の『永日小品』にイギリス留学中の話なども出てくる。昔読んだ「私の個人主義」なども思い出される。漱石の繊細さが感じられて、一人で言葉の通じない自分には「合わない」中で、周囲の期待と責任に押し潰されつつ過ごしていたのかと想像する。
・今回気になったのは、漱石の神経衰弱とその時期の家族への暴力、怒りの爆発について。まず「神経衰弱」という病。日常ではあまり聞かないけれど、今もあるのか? あるいは別の診断名に置き換わっているのか? 突然怒り出すのは神経衰弱とは関連するのか。関連しない場合は、別の疾患や障害の可能性はないか?
むしろその病や暴力と向き合ってみてもよいのでは。残念ながらこのあたりへの踏み込みはなくて、家族を愛し、家族に愛されたというふうにまとまっている。「怒ったときはちょっと怖い父だったけれど、子どもたちをとても愛していた」。
暴力については漱石亡き後に妻や子がエッセイ等で明らかにしているので、事実ではあったろうと思う。
今回の展示の中でも、
「怒り方が尋常じゃない」(純一)
「子供心にこのまま死んでくれたら」(筆子)
などの言葉も出てくる。一方で、四女の愛子は「そんな人じゃなかった」とも言っている。同居家族でもきょうだいの順番や親との関係性、過ごした年齢、あるいはその他の事情によって受け取るものが違うのだろうなと想像する。
物事は一面ではないので、「家族を愛し、家族に愛され」というのもまた事実だろうと思う。(いただきものをすると子どもたちがおいしいおいしいと食べたというお礼状などをよく書いているとか、子どもの名付けは適当でと言いつつ、16コも候補を挙げた手紙を送ったとか)ただ、創作が身近な者のケア、忍耐、犠牲などの上にあったということは、今まで見過ごされがちだったので、少し気になっている。むしろ創作と神経衰弱の関係を見せていったほうが、漱石が何に悩み、何が漱石を苦しめていたのかがわかり、またその時代背景も明らかになっていくと思うが、どうだろう。
今の時代だからこそ語るべき重要なテーマが含まれているように感じる。ジェンダー、家父長制、近代化、経済、労働、医療や健康など。遺族や子孫もいることだから難しいのかもしれないけれど。
・展示の最後のコーナーは略年譜が作られているが、単なる年表ではなく、「今回の企画」に合わせた内容になっていて、これを毎回学芸員さんが作っているのかと、その情熱に驚く。今回であれば、出来事だけではなく、日記や書簡にある家族に関する記述を引用して掲載されている。すごい。
・漱石が49歳で亡くなったことに驚いている。この時代の人は老いるのも(主には病気のために)亡くなるのも早い。時代に関係なく、向田邦子が亡くなったのが51歳のときということにも驚いた。とても歳上の人、という感じで生きてきたのに、いつのまにかもうすぐ追いつく。
▼漱石が住んでいた駒込千駄木の家(通称「猫の家」)には森鷗外も一時期暮らしていた。解体され、今は明治村に移築されている。
旧居跡の解説(文京区HP)
https://www.city.bunkyo.lg.jp/bunka/kanko/spot/ato/soseki.html
東京の都心に住んでいておもしろいのは、文豪と呼ばれた人たちや、文士の集った場所に今も気軽に行けて、当時を偲ぶ仕掛けがたくさんあるということだな。(もちろんここだけが文学世界ではないのは当然として)




次回は森田草平がフィーチャーされる。
平塚らいてうと心中未遂したけど、その顛末を小説にしたらと漱石に勧められて書いたという、ちょっとびっくりするエピソードの人としてしかわたしは知らないので、また展示で発見があるのを楽しみにしている。
ちなみに、2F上がったところの廊下に漱石の言葉の抜粋がボードに掲示されているスペースがあるのだけれど、その一つに森田草平への手紙の抜粋でこんなのがあった。
余は我が文を以て百代の後に伝えんと欲するの野心家なり
(明治39年10月22日)
そうなっていますよ!!!
ということと、こういう心情を吐露できる信頼できる相手としての森田に興味が湧く。
鷗外記念館や龍子記念館と並んで、ここも企画展示替えの度に訪れたいミュージアムになっている。