映画『トークバック 沈黙を破る女たち』鑑賞記録
*未見の方の鑑賞行動や感じ方に影響を与える内容です。
映画『トークバック 沈黙を破る女たち』を観た。
ドラッグ、依存症、レイプ、HIV / AIDS、孤立、虐待、貧困、前科、偏見・差別、DV...
人生は必ずやりなおせる!!
どんなに苦しいときでも、新しい未来が待っている
演劇で、声を取り戻していく"ワケあり"な女たちの物語
女たちのアマチュア劇団 ---それは芸術か、セラピーか、革命か?
アタシたちをなめんじゃない!
(映画公式チラシより)
2日後に、映画『トークバック』でゆるっと話そうという対話の場を控えていて、その準備のための鑑賞だった。
いささか直前すぎる準備だが、2014年の公開当時に一度観ているので、確認程度の作業になるだろうと思っていた。
ところが、メモをとりながら観ていて何度も、「あれ、こんなシーンあったっけ?」「こんなこと言ってたっけ?」となり、当時とは全く異なる感情に襲われている自分を発見した。
ああ、そうか、前回観た時、2014年当時。
わたし自身の人生がとにかく大変な状況だった。
何か一つシーンやセリフを観ても、そのことから想起される自分の問題に引っ張られながら観ていた。
だから映画の記憶がまだらになっていたのだ。
もちろん今回もいくつも引っ張られる部分はあった。
ほとんど、女性の人生に起こることぜんぶがてんこ盛りだ。
けれども、あの人たちの語りと踊りの全身の表現に、心地よくシンクロした。
痛みも喜びも後悔も希望も、ひたすら共に味わい、
観終わった直後は、おおお、わたしもますますtalk back, speak upするぜ!という気持ちになった。
映画の公開が2014年。
ハーヴェイ・ワインスタインの性暴力が告発されたのが2017年。
そしてさらに2020年の今。
それは暴力だ、それはゆるされない、わたしは黙らない、わたしのせいではなかった、もう偽らない…とほうぼうで声が上がって、それはもう止まらない流れ。
その時間を生きてきての今。
この映画について語ることは、社会の中でも自分の中でも、ないことにされてきたものを見つけること。
あのころのわたし、わたしたちに会いに行くことだと思った。
自分が罹患者か、経験者か、当事者かどうかに関わらず、ガンガン響いてくる言葉。
過去もわたしの一部、なかったことにするつもりはないわ
自分の声を取り戻すわ
彼女たちは私たちの延長戦だから
私がいきついたのは自分をゆるすこと、それは私の選択
泣いて気持ちを分かち合うことで成長できた
女として誇りを持って生きてほしいの
You keep me strong
......
沈黙しない。
表現として出すことで、普遍性を持つ。
あなたが辛い思いをしたのはわかる。
でもね、いつまでも犠牲者でいないで!
立ち上がれ!
カッコよくてセクシーな、ほんものの自分を起動させろ!
Stand up, Sisters!!!
挑戦する彼女たちから、勇気をもらう、励まされる。
Sisterhoodをわたしも感じた。
ダイナミズムは対話だけでも起こる。
でも演劇は、詩は、パフォーマンスは、思考判断を超えて、もっとダイレクトに届く。
感覚的で、感情的で、 自由で開放的。
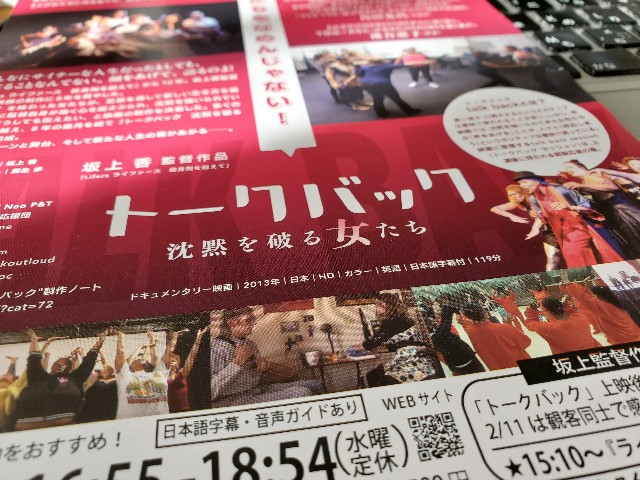
劇団の名前にも意味がある。
メデア・プロジェクト:囚われた女たちのシアター
The Medea Project: Theater for Incarcerated Women
王女メディアから取られている。
メディアは、エウリピデス作のギリシャ悲劇で、夫イアソンの不貞と裏切りに怒り、イアソンの婿入り先の娘を殺害し、さらに自分の息子2人も手にかけてしまう。
劇団の主宰者、ローデッサは言う。
「愛に溺れて自分を見失うこと、あるよね。でもわたしたちはメデアを責めない。女にとっての最終手段だから」
そう、非常時、戦時下で、女性が生き延びるために、やらざるを得なかったこと。
わかる。わたしたちだから、わかる。
このシーンは、とても印象深い。
杉山春さんの「満州女塾」が頭をよぎる。
このポストカードは、 先日行った松濤美術館の「サラ・ベルナール展」で買ったもの。サラ・ベルナール主演の舞台「王女メディア」のポスターの図柄で、彼女がその才能を発掘したアルフォンス・ミュシャが製作したものだ。
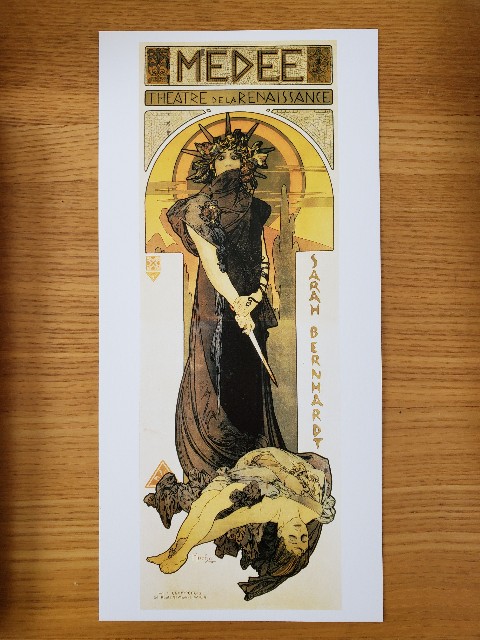
「トークバック」を見ることとこのときはつながっていなかったが、ローデッサの言葉を聞いた途端、思い出した。ああ、そういうことだったのか。
サラ・ベルナールはこの役をどんな思いで演じたのだろう。
また、昨年観た「私は、マリア・カラス」の中で、彼女が唯一出演した映画は、パゾリー二が監督した「王女メディア」だと知った。この頃の彼女は、オペラ界をほぼ追放された形で、新たなフィールドを求めての映画だった。
女性が自分のままに生きることが難しかった時代。
二人の女性の人生も、わたしの中でこの名に重なり、特別な意味をもって映画を受け取ることができた。
自分の担当患者とメデアプロジェクトをつなげた医師の存在も、今回とても印象に残った。
「HIVで死んだ人がいなかった」という発見、喪う悔しさ、無力感、医療の範囲を拡張する勇気。
懲罰的世界観の中では、誰が悪いかという話になる。
どっちが悪いか、どっちのせいか。
おれのせいだっていうのか。わたしのせいだっていうの。
誰が悪者かを決めるのと、
責任を問うことや引き受けることは違う。
修復的世界観の中で対話したい。
間違っても、失敗しても、やり直せる。
人生はいつだってやりなおせる。
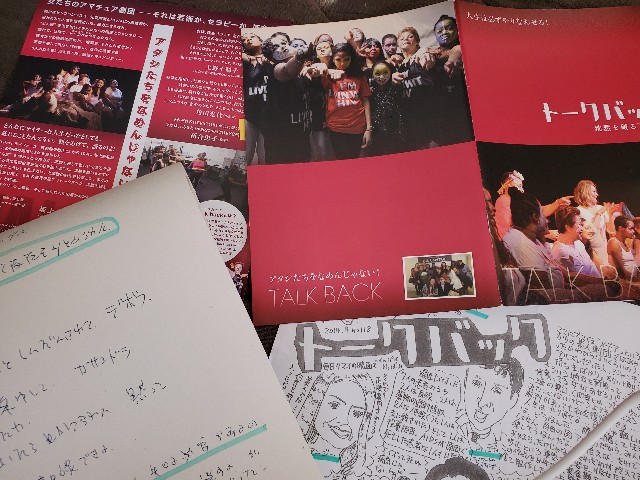
感想を自分の味わいながら、対話の場の前に、HIV / AIDSについての基礎知識を、対話の場の前提としてもっておいたほうがよいな、と気づいて、事前に調べておくことにした。
わたしも基本的なことは知っているつもりでいたけれど、1990年代ぐらいで止まっている気がした。
HIVとAIDSはどう違うのか?
"病=死"ではないとは、どういうことか?
HIV陽性者は妊娠できるのか?
わたしは、1987年代に出版された秋里和国の漫画「TOMOI」がきっかけで「エイズ」を知った。その頃はまだ治療法など解明されていないことが多く、エイズ=死の病と言われていた。
あのショックは十代のわたしにはとても大きかった。
さすがに今はそこまでではないにせよ、
これを機にみんなでアップデートすると、きっといいんじゃないか。
そして、前提があると、対話がもっと質のよいものになる。
映画『教誨師』でゆるっと話そうのときに、日本の死刑制度の基礎知識について共有したみたいに。
そう考えて、図書館で何冊か本を借りてきて、インターネットでも医療機関などを検索して、情報を集めた。
当日は、冒頭に5分ほど共有の機会を設けてからはじめることを、チュプキのスタッフさんにも伝えた。
当日の場もすばらしかった。
またレポートに書きたい。
(後日、書きました。こちら)
いやはや。
仕事で一つの場をひらくごとに、わたし自身、たくさんの学びをいただいている。
感謝しかない。
そしてまさかあの頃は、6年後にこんなふうにこの映画に出会い直すと思っていなかった。
人生は、わからない。
だから生き続ける価値がある。

追記:2/11 レポート
_____________________